アメンボに気づきましたか?
- 展覧会設計ゼミ

- 9月30日
- 読了時間: 8分
お初にお目にかかります。
ゼミ長の川田です。
アメンボがいたのに気づきましたか?
実は、水たまりに一匹、アメンボを放したんです。だれも気付いてないんですがね、こいつがちょこまかと動いて波紋をたてるせいで毎日冷や冷やしてるんです。アメンボはね、あれは跳ねてるんですよ。スイスイ滑ってるようですけど、よーく見てるとわかります。口から油を出してね、足先に塗って、水を弾いて跳んでるんです。
先日、私たちが心血を注いできた展覧会が無事開幕しました。本来であれば、まず協力してくださった方々への感謝や、これまでの活動の道のりをご報告すべきところですが、今回は少しだけ個人的な話をさせてください。
一つ目は、僕の放ったアメンボについてです。
実は、会場の床一面に広がるフィルムの、光が溜まって最も水たまりのように見える場所に、心の中で、一匹のアメンボを放しました。もちろん誰にも言っていません。来場者の方々も、まさか足元にそんな小さな生命がいるとは気付かなかったでしょう?こいつがちょこまかと動いては、静かな水面に繊細な波紋をたてる。そのたびに、私は誰かに見つからないかと一人で冷や冷やしていました。

これは完全に、ゼミ長という立場を逸脱した個人的ないたずらでした。設営を終えた、あの空間のフィルムがあまりにも本物の水たまりに見えたものですから、試さずにはいられなかった。本当にアメンボはここで生きていけるのだろうか、と。この行為には何の芸術的な意図もありません。ただ、禁じられた遊びのスリルと、誰もが気づきうる秘密を自分だけが知っているという、ささやかな優越感がありました。看視のふりをしながら、本当はアメンボの動きばかりを追いかけている。そんな秘密の楽しみを抱えて、私は展示室をうろうろしていました。
もう一つの報告はハエトリグモの「ピー助」との出会いについてです。
9月23日10時13分。会場湿度74%、会場温度21℃、曇り。
展覧会が始まって2日目の朝。看視スタッフとして105展示室の隅で本を読んでいた時のことです。視界の端で微かに動くものを捉えました。それは、見過ごすことのできない、確かな生命の動きでした。
近づいてみると、そこにいたのは一匹の小さく愛らしい、焦げ茶色のハエトリグモ。怪我をしているのか、おぼつかない足取りで前脚を庇いながら、餌ひとつない広大なフィルムの大地をひたすらに進んでいました。その健気さに、私はすっかり心を奪われました。
私には、自分のペットだと認識した生物に、雌雄の別なく「ピー助」と名付けてしまう悪癖があります。
自宅の庭で放し飼いにしていたニワトリのピー助。
小さな虫かごで育てた立派な角を持つカブトムシのピー助。
小学校の裏庭で、昼休みにパンやおかずの切れ端をあげていた黒猫のピー助。
そして今回、展示室を跳び駆けていたハエトリグモも、私のピー助になりました。
いつの間にかいなくなり、いつの間にか死んでいる、私のピー助たち。彼らが小さな水葬船に乗って、光の川を運ばれていく光景が、フィルムの上に幻視のように浮かび上がります。
翌日、ハエトリグモのピー助は、黒く萎びた小さな塊になっていました。エアコンの風に吹かれて隅に溜まった髪の毛や塵芥に混じり、ホコリの一部となっていました。

アメンボが立てる波紋。ピー助の小さな旅路とその最期。この展覧会、「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」は、ただフィルムが敷かれているだけの、極めてミニマルな空間です。しかし、何もないからこそ、そこではあらゆる些細な出来事が大きな意味を持って立ち現れます。水たまりに似たフィルムをただぼーっと眺めていると、不思議なものが見えてくるのです。窓の外を飛ぶ鳥の影がよぎり、遊覧船が水面を押し崩しながら渓流を流れ、目の表面に浮かぶムスカイ・ボリタンテスがすいすいと遊泳を始める。
この抑制されながらドラマチックで示唆に富んだ風景は、決して偶然に生まれたわけではありません。開催に至るまでには、数えきれないほどの困難がありました。


二つの展示案をめぐって意見が割れた時は、何時間にもわたって議論を重ね、実験を繰り返し、何とか一つのアイデアに絞りました。些細なメールのやり取りから、予算を調整して必要なお金を捻出する作業まで、我々の活動は一つとして欠けてはいけない重大なものばかりでした。
設営初日。何重にも巻かれた巨大で重たいフィルムのロールを、何人もの手で慎重に運び、シワが寄らないよう、息を殺してゆっくりと敷いていきました。関わった人全員が、翌日には筋肉痛になるほど過酷な作業でした。

設営2日目。フィルムの端を、床の境界線に合わせてミリ単位で切り揃えていく作業は、我々の中でも屈指の手先の器用さと、根気強さを持つゼミ生が担当しました。大きなモップをフィルムの上から押し付け、ずれないように、空気が入らないように、丁寧に、けれど力強く。繊細さと大胆さが同時に求められる作業は、みんなの神経をすり減らし、集中力を奪っていきました。

私たちは、だんだんと疲弊し、だんだんと散漫になり、フィルムと床の境界を見失い、フィルムがずれているのか、壁が曲がっているのか分からなくなっていきました。同じ光景に辟易し、感覚が麻痺してくるのです。午前9時に始まった作業は、簡単な昼食を挟んで午後2時、3時と過ぎていき、ようやく終わりが見えたのは、あたりが薄暗くなった午後6時ごろでした。
全ての作業を終え、ゼミ生全員で、105の静まり返った展示室に腰を下ろした時、窓から差し込む薄墨色の光がフィルムの上に広がるのを見て思いました。

「そうか、私はこの瞬間のために多摩美に来たのだ」と。
疲れきった体に、その美しさはあまりにも深く染み渡りました。
初めてゼミ生全員と顔を合わせた日のことを、今でもはっきりと覚えています。正直に言って、心の中は不安でいっぱいでした。それは人数が少ないという単純な問題もありましたが、一番の理由は、そこに集まっていたのが、一言でいえば「得体のしれない人たち」ばかりだったからです。
何を考えているのか読めないほど無表情な人、自分の興味のあることを熱っぽく語る人、やたらと芯をついた事を言う人。
共通の話題を見つけることすら難しいように思えました。このバラバラな個性が集まって、本当に一つのものを作り上げることができるのだろうか。そんな心配ばかりが頭にありました。
しかし、毎週金曜日に集まり、展覧会開催に向けて準備していく長く地道な道のりの中で、その印象はゆっくりと、確実に変わっていきました。
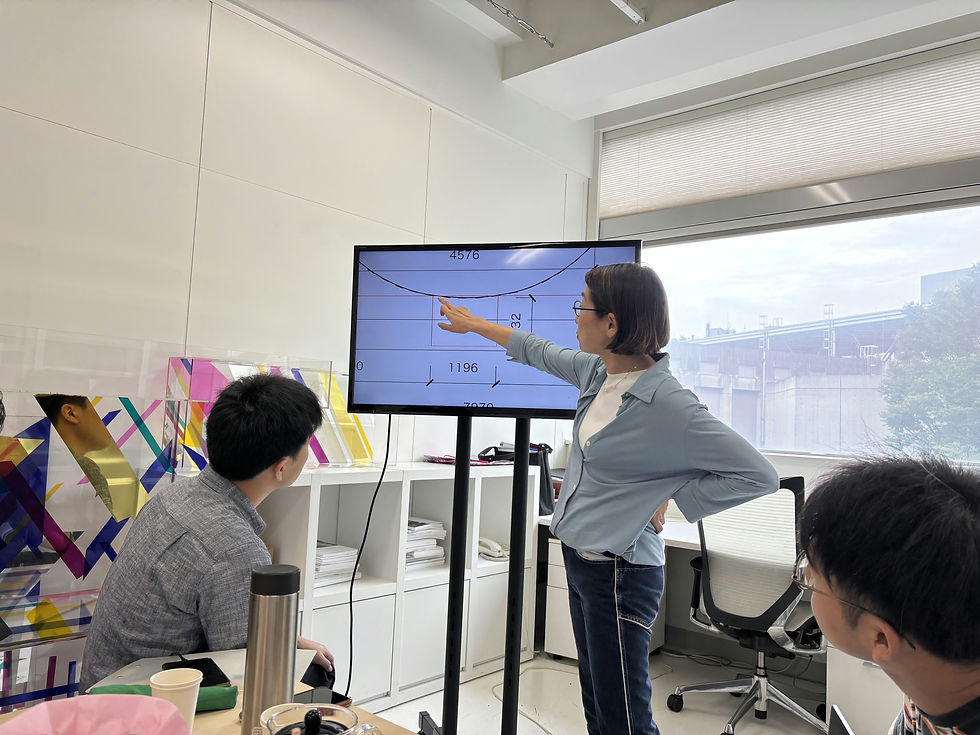
私たちは、もしかしたら気の合う「友達」にはなれなかったかもしれません。プライベートまでを深く共有するような関係ではなかったかもしれない。それでも、展覧会という一つの目的を共有し、背中を預け合える、少なくとも「仲間」にはなれた。私はそう確信しています。
生まれも育ちも、得意なことも思考の癖も全く違う人間が、ただ一つのゴールのために寄り集まる。そして、それぞれの知恵と情熱を注ぎ込み、一つの思考の粋とも言える展覧会を立ち上げる。そのプロセスは、奇跡のようでした。
展覧会の成功は、間違いなく彼ら一人ひとりの力によるものです。
誰もが見過ごしてしまうようなフィルムの僅かな歪みや、プロジェクトの根幹に関わる重要な懸念事項を、常に冷静な視点で見つけ出し、誰に言われるでもなく率先して修正していくゼミ生たち。
授業時間外でも、「この作業、やっておきますよ」と当たり前のように手を動かし、膨大な業務を淡々とこなし続けてくれた人。
会議が行き詰まり、全員が思考停止に陥った時、いつも鋭い指摘や誰も思いつかなかった視点を投げかけて、私たちの議論を進めてくれた人。
それぞれが自らの持ちうる力を惜しみなく発揮し、自分にできないことは他者を信頼して託す。そうすることで、個人では到底たどり着けない、素晴らしい景色を見ることができました。
翻って、ゼミ長であった私自身を振り返ると、ほとんど何もしてこなかったように思います。特段、仕事の要領が良いわけでも、卓越したアイデアがあるわけでもない。ましてや、あの個性豊かな面々をぐいぐい引っ張っていくようなリーダーシップは、私にはありませんでした。
私がしてきたことと言えば、この「得体のしれない」、しかし誰よりも信頼できる仲間たちの力を、ただ信じきることだけだったのかもしれません。彼らならきっと何かを生み出してくれると信じ、それぞれの才能が存分に発揮される「場」をどうにか守り抜くこと。それが、何もできない私に唯一できた、ゼミ長としての仕事だったと、今、確かに感じています。
この仲間たちと展覧会を作り上げられたことを、心から誇りに思います。みんなありがとう。
この展覧会は、多くの人々の協力の上に成り立っています。私たちの無理な相談にも親身に応じてくださった芸術学科研究室の方々、アートテーク施設関係者の皆さん。毎朝、展覧会のバナーを丁寧に設置してくださっている守衛の方々。そして何より、この空間に足を運び、この空間で過ごしてくださった皆さん。
我々、家村ゼミ一同より、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

多摩美術大学芸術学科4年 川田宗志郎



コメント